商学部NEWS
市原ゼミが文京キャンパスのセミの鳴き声を調査しました
2022.08.25(木)
NEWS
今回の調査には2つの目的があります。
①都内(文京キャンパス)にはどのような種類のセミが生息しているのか確認する。
※埼玉県地球温暖化防止(関東圏の地球温暖化調査)推進事業への貢献
②音を文字で表現し、表現することの難しさを学ぶ。
※日本語学ゼミの学修領域
上記の①②について、事前学修を午前中に行い、午後からキャンパス内の樹木がある場所を調査しました。今回はセミの声に着目した活動です。
まず、地球温暖化防止の観点から、セミの鳴き声を考えてみます。文京キャンパスでは6月半ばからセミが鳴き始めました。去年は10月半ばまでその鳴き声を聴くことができました。セミは、25℃~35℃で活発に動きます。セミの声と気温を照らし合わせると、少し変なことになっていることに気づくはずです。
次は、日本語学的な観点からセミの鳴き声を考えてみます。このセミの鳴き声ですが、セミの姿を文字で表現することは何とかできますが、鳴き声を表現しようとすると、十人十色になってしまいます。それだけ、音を文字で表すことは難しいことなのです。
以下に本日の一例を紹介します。
【アブラゼミ】
姿:よく身近に見られるセミで、体は黒地に白が入り混じっている。羽が茶色のセミ。
鳴き声:
例1)ジィジィジィジィ~
例2)シリシリシリシリシリ~
例3)ザワザワザワジジッ~
例4)ジョジョジィビビ~
【ミンミンゼミ】
姿:体は全体的に黒っぽく、翅の上の硬い部分には緑色の模様がある。翅は透明で所々茶色い水玉模様がある。
例1)ミーンミンミンミンミーン~
例2)ビ~ンビンビンビンビーン~
例3)ビューンミュンミュンミュンビューン~
そのほかに、本学のキャンパスでは「ニイニイゼミ」「ヒグラシ」「ツクツクホウシ」が確認できました。幸いにも、東海地方以西から九州にかけて平野部に広く分布する、ミンミンゼミより一回り大きなクマゼミが、この文京キャンパスでは確認できなかったことに安堵しています。地球温暖化に伴い、近年その生息域の北上が危惧されています。
そして、その記録を付ける過程で音声を文字に起こすことがどれだけ難しいかも学ぶことができたのではないかと思います。文字で表されていることが全てではないこと、また、表記に私たちは騙されがち?!であることも理解できたようです。
みなさんも家の玄関の扉の鍵をかける音をどのように正確に表現できるか想像してみてください。よく、「カチャ」と表現されますが、それは正確な表現ではないことがわかるでしょう。また、洗濯機の音も、「ジャブジャブ」だけではなく、本当ならば、水の細かな音も表現する必要があります。
本日は、「ゼミの鳴き声」から2つのことを学んだことについて報告しました。
 文京キャンパスのツクツクホウシ
文京キャンパスのツクツクホウシ
 文京キャンパスの「セミの鳴き声」調査場所
文京キャンパスの「セミの鳴き声」調査場所
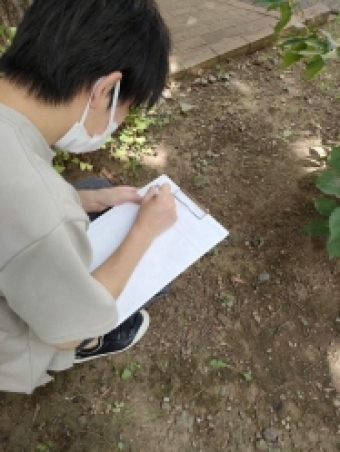 セミの鳴き声を記録するゼミ生の姿
セミの鳴き声を記録するゼミ生の姿
 アブラゼミがたくさん生息する樹木
アブラゼミがたくさん生息する樹木
①都内(文京キャンパス)にはどのような種類のセミが生息しているのか確認する。
※埼玉県地球温暖化防止(関東圏の地球温暖化調査)推進事業への貢献
②音を文字で表現し、表現することの難しさを学ぶ。
※日本語学ゼミの学修領域
上記の①②について、事前学修を午前中に行い、午後からキャンパス内の樹木がある場所を調査しました。今回はセミの声に着目した活動です。
まず、地球温暖化防止の観点から、セミの鳴き声を考えてみます。文京キャンパスでは6月半ばからセミが鳴き始めました。去年は10月半ばまでその鳴き声を聴くことができました。セミは、25℃~35℃で活発に動きます。セミの声と気温を照らし合わせると、少し変なことになっていることに気づくはずです。
次は、日本語学的な観点からセミの鳴き声を考えてみます。このセミの鳴き声ですが、セミの姿を文字で表現することは何とかできますが、鳴き声を表現しようとすると、十人十色になってしまいます。それだけ、音を文字で表すことは難しいことなのです。
以下に本日の一例を紹介します。
【アブラゼミ】
姿:よく身近に見られるセミで、体は黒地に白が入り混じっている。羽が茶色のセミ。
鳴き声:
例1)ジィジィジィジィ~
例2)シリシリシリシリシリ~
例3)ザワザワザワジジッ~
例4)ジョジョジィビビ~
【ミンミンゼミ】
姿:体は全体的に黒っぽく、翅の上の硬い部分には緑色の模様がある。翅は透明で所々茶色い水玉模様がある。
例1)ミーンミンミンミンミーン~
例2)ビ~ンビンビンビンビーン~
例3)ビューンミュンミュンミュンビューン~
そのほかに、本学のキャンパスでは「ニイニイゼミ」「ヒグラシ」「ツクツクホウシ」が確認できました。幸いにも、東海地方以西から九州にかけて平野部に広く分布する、ミンミンゼミより一回り大きなクマゼミが、この文京キャンパスでは確認できなかったことに安堵しています。地球温暖化に伴い、近年その生息域の北上が危惧されています。
そして、その記録を付ける過程で音声を文字に起こすことがどれだけ難しいかも学ぶことができたのではないかと思います。文字で表されていることが全てではないこと、また、表記に私たちは騙されがち?!であることも理解できたようです。
みなさんも家の玄関の扉の鍵をかける音をどのように正確に表現できるか想像してみてください。よく、「カチャ」と表現されますが、それは正確な表現ではないことがわかるでしょう。また、洗濯機の音も、「ジャブジャブ」だけではなく、本当ならば、水の細かな音も表現する必要があります。
本日は、「ゼミの鳴き声」から2つのことを学んだことについて報告しました。
 文京キャンパスのツクツクホウシ
文京キャンパスのツクツクホウシ
 文京キャンパスの「セミの鳴き声」調査場所
文京キャンパスの「セミの鳴き声」調査場所
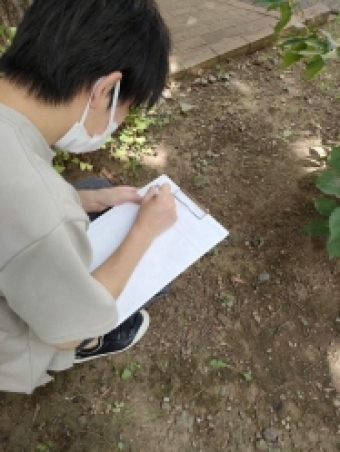 セミの鳴き声を記録するゼミ生の姿
セミの鳴き声を記録するゼミ生の姿
 アブラゼミがたくさん生息する樹木
アブラゼミがたくさん生息する樹木